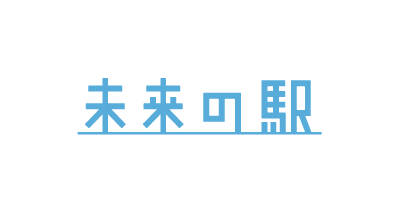

【With/AfterコロナにおけるNew Normal #2】臼井教授に聞く、新たな「働き方・働く場」とは?
前回に続き、本研究のアドバイザーである日本大学法学部の臼井哲也教授にWith/Afterコロナでの「学び」「働く」「買う」「遊ぶ」といった分野におけるNew Normal(新しいあたりまえ)についてのインタビューです。本稿では、「働き方・働く場」について紹介いたします。
プロフィール
日本大学法学部 臼井哲也(うすいてつや)教授
専門は国際マーケティング論。1971年兵庫県生まれ。高校卒業後に渡米し,米国ジョージア南大学経営学部を卒業。帰国後に起業,その後小田急エージェンシー勤務を経て,明治大学大学院商学研究科博士前期課程・後期課程を修了する。桜美林大学専任講師,日本大学法学部専任講師,准教授を経て,2016年より現職。多国籍企業学会会長,国際ビジネス研究学会理事。現在はビジネスモデルの国際化における諸課題を研究テーマとしている。
取材・文=田村高志
※取材は6月1日にリモートにて実施いたしました。
●コロナ禍による働き方、働く場の変化シナリオ

「これからは、ジョブ・マネジメントが鍵。対面で会うことの必要性は“擦り合わせ”」
田村:前回は「学び方・学ぶ場」についてお聞きしました。次に「働き方・働く場」の変化について、どのようなシナリオが想定されるかをお聞きしたいと思います。
臼井先生:このインタビューもそうですが、リモートワークは増加していきますので、実際に会う場面はコロナ前よりも減少すると思います。ただし、実際に対面で会うことは決してなくならないと考えています。重要なのは、何のために対面で会うのか、その目的と適性が問われるということであり、これら方式の使い分けにあります。リモートでやること、対面で行うこと、これらを適正に合わせて使い分けるジョブ・マネジメントが鍵となるでしょう。
田村:どのようなことが対面で会わないといけないと思われますか?
臼井先生:それは、職種や仕事(業務)の内容によると思います。例えば、プログラマーはリモートでも仕事ができますが、エンジニアは機械を触りながら仕事を進める必要がありますね。この場合は擦り合わせが必要なので、対面で一箇所に集まる方が効率的ですね。つまり、「擦り合わせ」がリモートと対面を分かつひとつのキーワードとなると思います。日本企業はもともと擦り合わせが得意であり、また擦り合わせを通じた仕事の進め方に慣れています。
擦り合わせがあまり重要視されない仕事では、分業が明確であるため、ブロックのように「これは私が担当します。あなたはこれとこれを組み合わせてください。」といった仕事の進め方ができますね。これはアメリカ型といっていいでしょう。一方、日本企業では部門間や担当者間での緊密な擦り合わせを好む傾向にありますね。実際に会うかどうかは、仕事の内容に合わせて、擦り合わせがどこまで必要かということで決まるのではないでしょうか。
田村:プランニング業務に当てはまると、データ収集・現状分析、現状確認、課題の抽出までは分業可能でリモートで十分できる感覚をもっています。リモートでは難しいと思うのは、コンセプトやアクションのアイディア開発の領域です。手法としてはワークショップをよく実施しますが、これは一か所に集まった方が、創発が生まれやすいのではと感じています。
臼井先生:なるほど。リモートの方がやりやすいことと、対面の方がやりやすいことの両方がありますよね。メールが誕生したときがそうでしたが、すべてがメールになるわけではなく、コミュニケーションツールのひとつとして使い分けている感覚だと思います。LINEもそうですね。ただし、現在のオンラインツール(Zoomなど)はメールに比べて圧倒的に実際に会っている感覚でコミュニケーションがとれることは大きな違いです。
田村:優れた製品はオンラインでの営業でも売れると思う一方、広告会社などソリューションを提供している業種の営業は、日々のコミュニケーションのなかでクライアントの課題を引き出して、そこに応えていくといった、人間的でリアルなコミュニケーションが重要だと思っています。
オンライン会議をやっていて感じるのは、無駄が無いので非常に生産性は高いと感じる一方で、心理的距離感を縮めるのには難しさを感じます。対面営業ですと、雑談から信頼関係が構築し、新しい業務が生まれることもあるので、リモートだけでは業務の拡張は難しいのではと感じています。
臼井先生:「擦り合わせ」というのは、まさにそういうことです。もともと「擦り合わせ」という用語は東京大学の藤本隆宏先生が自動車メーカーのものづくりを観察することから、発見なさったマネジメント・コンセプトです。部品と部品が緊密に調整された結果、完成車としての品質が高まるのです。あらかじめ決められたブロック(部品)とブロック(部品)を事後的に組み合わせるような方式では、高品質な自動車は製造できません。部品の開発担当者同士が何度もあって、まさに擦り合わせていく作業プロセスこそが高品質なものづくりの秘密なんです。しかしこれにはコストがかかりますね。
同様にソリューション型の営業においても、お客さん自身のニーズがなかなか明確に表現できない。それを営業担当者が聞き出していく。このようなプロセスを通じて新しいソリューションのかたちが徐々に出来上がっていく。このような場合は対面での繰り返しのコミュニケーションが欠かせないのではないでしょうか。
多くの場合営業職では、お客さんにフィジカルに、それも何回も繰り返し会ってこそ信頼関係が構築できるのではないかと思います。そのことと、タスクとしてオンラインでのやりとりでできるものの線引きができてくれば、毎日、定時に会社へ行く必要はありませんよね。職種にもよりますが、週に3日しか出社しなくていいということは十分にあり得ると思いますし、実際にアメリカのIT業界ではそのような働き方が定着していますね。

「“組織慣性”によって元通りになる可能性も」
田村:このまま一気にリモートワークがスタンダートになるのでしょうか?
臼井先生:ひとつ面白い話があって、国際経営を研究している友人が、アフターコロナにおけるグローバル企業での働き方について簡易的な調査をしています。日本企業の海外現地子会社には日本人の駐在員が滞在していますね。アフターコロナにおいては、リモートワークの利点が認識され、駐在員たちを引き上げるのではないかと予測していたところ、もう1度日本から現地へ駐在員を送り込もうと、今までのやり方に戻そうとする傾向にあるそうです。日本の駐在員はコストが高いので、これを機に、引き揚げる動きになると思ったのですが、まったくそういう動きは見られないようなんです。
合理性にかかわらず、現状を維持しようとする組織的な性質を「組織慣性」といいますが、日本の組織ではコロナが終わったら、また元に戻ってしまう力が働くのではとも考えられます。人間は器用ではありませんので、コロナ禍が完全にあけると、あっさり元に戻ってしまう可能性がありますね。例えば、ZOOMを1週間使っていなかったら、もう開くのが面倒になるかもしれません。一方で、一部のクレバーな人、スマートな人は、上手に対面とリモートを使いこなしていくようになると思います。このような組織慣性の働きは、業界や職種、企業規模、そして個人の能力によっても大きく異なると思います。
田村:実際、会議において数人が会社にいて、あとはそれぞれが自宅にという時にやりにくさを感じています。恐らく、営業は出社ベースになると思いますので、スタッフ部門もそっちに引っ張られ、結局全員が出社している状態になるのではとも感じています。
臼井先生:組織慣性が働くと、そうなる可能性は十分にありますね。また機能的にもZoomなどのツールを使うことが対面の会議よりもまだ劣っている面もあるので、みんな集まっちゃったほうが早いという結論になるかもしれません。
田村:あと、ひとりだけリモートだと、その人は置いてきぼりになる気もします。
臼井先生:それは重要な指摘ですね。たしかにオンラインでやるなら全員がオンラインじゃないとスムーズにコミュニケーションがとれないですね。あくまでも現在のZoom機能での話ですが・・・・。
田村:お話を伺っていて、対面で会うということは意外と減らないのかもしれない、と感じてきました。
臼井先生:その職種や業務内容において、どこまで擦り合わせが必要なのか、全体として多いか、ということですね。たとえば私の仕事は、擦り合わせは少ない方です。タスクが明確にわかれていますから。論文を書くために、ロンドン在住の共同執筆者とオンラインで打ち合わせをするのですが、それは1カ月に1回で十分ですね。あとは分業してやりましょう、と。そういう仕事のやり方であれば、会社に行く必要がありませんね。そういう人たちの人数はどれくらいなのかは調査しないとわからないですが、人数としても、全体の仕事に占める時間の割合もあまり多くないということであれば、通勤客は1割くらいしか減らないかもしれませんね。
「信頼関係の構築はオンラインだけでは難しい。営業マネジメントが勝負の鍵」
田村:営業は、より人間的な魅力が問われるようになると感じました。
臼井先生:営業担当者の人間的な魅力はとても重要ですが、だからと言ってオンラインが必要ないかというと、そうでもないと思います。日本でもオンライン商談のシステムを販売する会社が増えてきましたね。田村さんご自身もオンラインのみで成約までいたるなんて、一部の商品に限られると思いますよね。ましてやB to Bでのクライアントとの信頼関係構築を考えるとオンラインだけでは難しいのは明白です。
アメリカでは「インサイド・セールス」、いわゆるテレフォンアポインターのような内勤の営業に対する需要が高まっています。アメリカの企業では、営業職であっても明確にタスクに線が引かれる傾向にあります。「私はポイントゲッターです。見込み客に対し繰り返しコンタクトをして、ファーストミーティングを取り付けます。そして次の担当者へつなぎます」といった分業体制ができています。会社のなかでの分業体制が明確であればあるほど、オンラインの活用に向いています。要は、営業職であっても、必要に応じて、オンラインと対面の営業を使い分けて、営業プロセス全体を効率化、見える化することが必要なのではないでしょうか。
営業の生産性を考えると、私は、アフターコロナにおいてこの適切な使い分けの営業マネジメントが勝負の鍵を握るようになると思います。適材適所で個人個人の能力を引き出すことができる会社は若者にも選ばれると思います。選択肢が広がったので、その選択肢をどこまで使いこなすことができるか、ということだと思います。
●働く場と通勤の変化シナリオ

「働く場の選択肢の拡張、それによる定点(会社)への通勤頻度の減少」
田村:通勤者の数が減少するのではないかと鉄道会社のグループの人間としては危惧しているのですが・・・
臼井先生:アフターコロナの通勤において大前提になるのは、「選択肢の拡がり」ですね。先ほどもご紹介しましたように、オンラインやリモートに向いていること、不向きなことの区別が明確になっていくでしょう。よって、通勤量が減るのは間違いないでしょう。それが、2割なのか3割なのかはわかりませんが、1週間のうち在宅勤務を半分認めますという大企業について報道されていますので、そのくらいの幅で減ることも十分にあり得ると考えています。
田村:今まで、鉄道会社にとっては定期券収入が大きな収益基盤でした。ただ、通勤者が必ず定期券を買うというわけではなくなるということが予測されます。
臼井先生:定期券は毎日乗ることを前提としているので、今まで定期代を支給していた企業は、回数券の方が安いならそちらの購入を従業員へ求めるでしょう。逆にいえば、鉄道会社側は、週に2回、3回だけ使えるような定期券、回数券のような新しい価格デザインを提案していくという流れになるのではないかと考えます。
田村:企業は、経費削減になるほうを選ぶということですね。
臼井先生:企業は当然、経費削減になるほうを選ぶと思います。ただし、通勤や勤務中の労災の問題もあり、法律家にこの辺りは確認の必要はありますが、いずれにしても経費削減のほうで動いていくことになるかと思います。
「“擦り合わせ” “分業” “組織慣性”の概念が、変化を洞察するヒント」
田村:一方で、先ほどの「組織慣性」のお話をお聞きして、そこまで大きな減少をしないのではという感じもします。
臼井先生:そうですね。組織慣性は、歴史ある大企業であればあるほど、効いてきます。一方でスタートアップ企業は柔軟にルーティンを変えてくると思います。若者も適用が早いと思います。また、通勤者の数が大幅に減らないとすれば、それは「擦り合わせ」が必要だからということになりますね。「擦り合わせ」がどうしても必要で、擦り合わせに価値を見出している仕事の場合は、物理的な「場」に集まることが大事になると思います。もちろん、これをテクノロジーがどこまで超えていけるのかは、今後の技術課題になりますね。
田村:大半のビジネスマンは、週5日あったら3日は会社へ行くのではないかと感じました。
臼井先生:そうですね。少なくとも週1回の在宅はありえるでしょうね。仮にすべてのワーカーが週2日在宅になれば、単純計算で通勤量は4割の減少になりますよね。もちろんこれにはより精緻な分析が必要ですが、「擦り合わせ」、「分業」、「組織慣性」などの概念は、分析を行う際のヒントになると思います。

「駅には、ラウンジ的な雰囲気のワークスペースが求められ、マルチプレイスへ」
田村:世帯構成によっては在宅よりサテライトオフィスを使う方が良いという人もいるかと思います。
臼井先生:その通りですね。私も在宅勤務を約2ヶ月間続けていますが、家族と常に一緒だと、仕事において不便な面も多々ありますね。プライベートなことなのでこれ以上は発言しませんが・・(笑)。小さなお子様を抱えておられるご家庭では尚更ではないでしょうか。自宅の最寄駅にサテライトオフィスやコ・ワーキングスペースがあるといいですね。
アフターコロナでは、これを前提として駅の在り方を考える必要があります。働く人の中継地点、憩いの場。駅はそういうふうに作り変えていくべきではないでしょうか。
田村:主要駅には、サテライトオフィス、コ・ワーキングスペースは標準機能にすべきかと。
臼井先生:人によってはスタバ、という方もいますが、私がもっとも集中できるのは空港のラウンジなんです。到着してから2、3時間で搭乗することが決まっていますので集中できるんです。ラウンジに行くとほとんどビジネスパーソンばかりなので、落ち着きます。ああいう空港のラウンジ的な雰囲気は駅には合うと思いますし、時間を決めて集中して取り組む空間はますます必要になると思いますね。
田村:集中してやるときは場を変えたほうがいいですよね。
臼井先生:そうです。スタバのサードプレイスのコンセプトがもともとそうですよね。リモートワークの一般化は、鉄道ビジネスへの影響が大きいことは間違いないですね。複数の駅にそのような場所があれば、サードプレイスが複数利用できる「マルチプレイス」になりますね。
田村:輸送だけでなく、オフィス賃貸など不動産事業にも関わってきますからね。
臼井先生:私たちの共同研究論文で提案している「LDKステーション」*のような機能が求められていますし、それを持たないと、従来型の駅直上の不動産の価値は徐々に下落してくることは避けらないと思います。単に乗降客数が1、2割落ちてくるということではなく、そもそも駅に滞在しなくなる可能性があります。ICTによる最適化社会では、今まで以上に駅は通過地点になってしまう可能性があると思います。すでにあらゆるものがオンラインで注文でき、指定した時間と場所に届きますからね。
リアルの場で、ビジネスパーソンや生活者に快適に過ごしていただく機能を拡充することなくして、駅の場としての価値の再創造は望めませんね。逆に言えば、アフターコロナにおいては、「LDKステーション」が生活者の仕事と暮らしのパートナーになることが求められているのではないでしょうか。
田村:その通りですね。手前みそですが、我々の「未来の駅」研究の価値が、今回のコロナ禍によって一層高まった感じがしています。「働く」については以上としまして、次に「買い物・レジャー」についてお
聞きしたいと思います。
以上、臼井先生からWith/Afterコロナにおける「働く」の変化シナリオについてお聞きしました。次号においては、「買い物・レジャー」についてのインタビューをご紹介します。
*田村高志・吉村寿垣・立花徹也・増田光一郎・甲斐美由紀・臼井哲也(2020)「未来の駅が創造する価値の研究-LDKステーションと沿線多拠点生活の可能性-」『日経広告研究所報』310号、311号