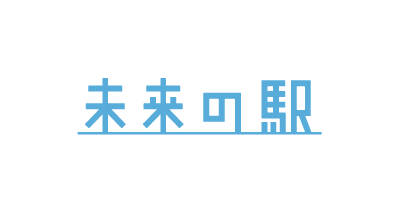

【With/AfterコロナにおけるNew Normal #3】 臼井教授に聞く、新たな「買い方&買い場」とは?
前回に続き、本研究のアドバイザーである日本大学法学部の臼井哲也教授にWith/Afterコロナでの「学び」「働く」「買う」「遊ぶ」といった分野におけるNew Normal(新しいあたりまえ)についてのインタビューです。本稿では、「買い方・買い場」について紹介いたします。
プロフィール
日本大学法学部 臼井哲也(うすいてつや)教授
専門は国際マーケティング論。1971年兵庫県生まれ。高校卒業後に渡米し,米国ジョージア南大学経営学部を卒業。帰国後に起業,その後小田急エージェンシー勤務を経て,明治大学大学院商学研究科博士前期課程・後期課程を修了する。桜美林大学専任講師,日本大学法学部専任講師,准教授を経て,2016年より現職。多国籍企業学会会長,国際ビジネス研究学会理事。現在はビジネスモデルの国際化における諸課題を研究テーマとしている。
取材・文=田村高志
※取材は6月1日にリモートにて実施いたしました。
●コロナ禍による買い方、買う場の変化シナリオ

「拡がった選択肢、さらに賢くなった消費者」
田村:前回は「働き方・働く場」についてお聞きしました。次に「買い方・買い場」の変化について、どのようなシナリオが想定されるかをお聞きしたいと思います。
臼井先生:「働き方・働く場」の話ともつながってきますね。今回の外出自粛によって、おうちで楽しめることをみんなクリエイティブにやりましょうという方向になって、おうちでの様々な楽しみ方が企業や自治体などからも提案され、みなさん、実践してきました。それによって様々なことがおうちにいながらにしてできることに多くの生活者が気付いたと思います。初めてアマゾンのプライムビデオを契約した方、これに飽き足らずネットフリックスやDAZNも契約したという方もおられると思います。いずれにしても、様々な経験を「してしまった」というのが適切な表現でしょう。オンラインでの環境を、いかにしてフルに使いこなすかを考えるという経験を、すべての生活者が「してしまった」ということは、外出を伴うリアルな場での買い物にとっては逆風になると思います。
ただし、揺り戻しも当然あると考えられます。買い物は、やっぱり外へ出るのが気持ちいい、ストレス発散になる、ということを改めて認識したということはリアル店舗にとってはプラスに働くと思います。とはいえ、オンラインで様々なことができると「知ってしまった」ので、生活者はさらに賢明な購買行動をとるようになるでしょう。
知人が書店で働いているのですが、外出自粛規制の最中であっても、ロードサイドの書店にはネットを苦手とするシニア層の生活者は変わらず来店しているようです。このようにネットが苦手な生活者は存在しますよね。しかし、オンライン生活を経験「してしまった」ことで、ネットを使わない生活者はさらに減少することが予測されます。リアル店舗には、ここにしかない独自性をさらに追求する努力が求められます。利便性や機能性とは異なる、「感動」や「心地よさ」を演出する仕掛けですね。
近年、書店は、楽しい売り場づくりに努力していますね。書店員による手書きのポップ掲示や本の陳列方法(ディスプレイ)による演出、書店でしか手に入らない付録、カフェ風にして読み比べてから購入できる売り場づくりなど、リアルな場ならではの仕掛けが重要となっていますね。このように売り場づくりにどれだけ投資ができるかが勝負の鍵になっていますね。
田村:たしかにリアルな買い場に行く目的は、モノの充足もありますが、そこで人と人との交流があったり、予期せぬ発見があったりといった充実した時間が過ごせるというのもありますよね。しかしながら今度は、人は多いけど売上があがらないという課題が出てきます。
臼井先生:その通りです。たとえば、ショッピングモールでは、集客力に加えて、買い上げ率や客単価の向上にも努力しています。一般にショッピンモールでは、まずは集客をはかるためにイベント等を開催します。次に、来店したお客様にいかに買っていただくかという2段階の取り組みを行っています。その仕掛けとして、店員の接客スキルと館全体としての仕掛けがありますね。館全体としての仕掛けについては、広告会社の腕の見せ所になると思います。集客プラス、売り場で来店者にどうやってご購入いただくのかという仕掛けにこそ、クリエイティビティがもっとも求められるのではないでしょうか。古典的には福引などですが、より進化した面白い仕掛けが求められるでしょう。今しか、ここでしか買えないという演出を徹底して、矢継ぎ早に店頭で展開していかないと、来店者は館内を散歩して帰宅するということになってしまいますね。ショールーミングの加速です。
田村:いっそのこと、入場料を頂いても良いのではと。
臼井先生:ある大手小売業のマネジャーは、「ディズニーランドが羨ましい」とおっしゃっていました。テーマパークは入場料ビジネスですが、小売業はいかに優れた売り場を開発しても、無料で提供することになりますからね。あくまでもプロモーションの一環なのです。辛いですね。
今後は、小売業でも入場料のビジネスモデルをもっと積極的に実験するべきではないでしょうか。ビジネスモデルの研究のひとつの分野に「収益モデル」があります。以前、「フリーミアム」という価格デザインが話題になりましたね。オンラインゲームの世界でも、またアマゾン・プライムでも、その成功の鍵は価格デザインにありますね。無料ゾーンと有料ゾーンを設ける、あるいはプレミアム会員に特典をつけるなど、いろんな方法を試してみるべきですね。
田村:コストコは年会費とりますよね。
臼井先生:それこそが、コストコのビジネスモデルですよね。我が家も会員ですが、年会費を支払ってまでも月に1回は行ってみたいというだけの驚きの品ぞろえがコストコにはありますね。しかも、コストコにしかない商品があります。2011年にライターの中沢さんと社会学者の古市さんが「遠足型消費」というコンセプトを提唱しました。ママ友が一台の車で30分ぐらいかけてコストとに行って、2時間くらいで帰ってくるという日常の遠足気分がコストコの魅力なんだと分析していました。非日常空間は体験したいが、でも遠出や旅行にはお金がかかってしまうと考える生活者にとって「遠足型消費」は魅力的ですね。
コストコには、レジャーとしてのショッピングで買わせる仕掛けもありますね。ありきたりのものはアフターコロナの世界では、さらに厳しい状況になっていくでしょう。コストコには非日常空間が広がっており、その場に行きたい仕掛けが満載ですね。月1回、車でちょっと遠出をしてコストコへ行くときには「ワクワク感」がありますよね。

「鍵となるのは、販売スタッフも含めた店づくり」
田村:丸井は、「売らなくてもいい店」を志向し、接客も「買わせようとしない」という方針をされていると聞いたことがあります。
臼井先生:アフターコロナにおいて、あらゆる小売業は、お客さんとお店の間の関係づくりが鍵になると考えています。とくにアパレルや美容院の場合は、特定の販売員やスタッフを目指して来店するお客さんがおられますよね。リアルの売り場では、昔の商店街のように、販売員の人間的な魅力に回帰するのではないかと考えています。
丸井は販売員の接客力を磨くことに加えて、PBを積極的に展開しており、在庫の状況もすぐに確認できるなど、早い段階からオムニチャンネルの開発に力を入れてきました。試着も返品もネットと店舗で完結するシステムを構築しています。
ただし、これはPBだからできるという面もあります。同じものがネットで手に入る仕入れ型の小売業には勝手が違うと思います。この問題は小売業のビジネスモデルに関わってきます。イオンは自社のPBである「トップバリュ」を国内外で販売できるように、グローバルなレベルで力を入れています。やはりどこでも手に入るナショナル・ブランドだけの品揃えだと、独自の売り場づくりが難しく、選ばれる店舗にはならないため、いい商品を自分たちで開発して店頭に出すのは、リアル店舗の生き残りの有効策になります。食品スーパーで言えば、お惣菜や生鮮の店内調理がますます重要になると思います。昔の魚屋さんですね。生活者は「市場(いちば)」の独特で非日常的な雰囲気を近場で楽しみのではないでしょうか。
PBという点でいえば、ファーストリテイリングのような製造小売業は、ネットと店舗を使い分けて、お客さんへ価値を提供するには適したビジネスモデルです。三井アウトレットパーク横浜ベイサイドにユニクロとGUの複合店舗(UNIQLO PARK)が4月にオープンしました。注目すべき店舗ですね。お店の周辺には人工的な水辺があり、店内にはアトラクション的なセルフレジ、屋外にはすべり台があります。子供たちが楽しめる仕掛けが満載で、エンターテイメントとショッピングが見事に融合された店舗になっています。

「駅の価値は、人が集まりやすい場所。それを起点に再デザインをする」
田村:最近の店づくりには、エンターテイメント性がありますよね。一方、旧来の駅ビルはそういう演出がしにくい構造に思われます。今までは、駅直結でワンストップで買える利便性・効率性を追及してきたため、構造上に余白がない施設が多いです。
臼井先生:たしかにそうですが、駅は人が集まりやすく、アクセスの良い場所であることが最大の魅力です。シニアやママ友が集まるのも、帰宅途中に立ち寄るのも、やはり駅ですよね。駅は、鉄道・バスといった交通インフラのハブですから、そこには独自の価値があります。みんなが「日常的に集う場」としての価値に特化して作りこんでいくべきだと思います。その価値をわかりやすく伝え、より多くの方に日常的に来ていただき、かつ消費いただくビジネスモデルの構築を目指すべきですね。キーワードは「毎日」ですね。また、お客さんとの関係性を構築していくには、店ではなくスタッフのブランドを重視するのも得策ですね。「あの店舗のあのスタッフの皆さんの心地よい雰囲気を毎日感じていたい」といった感情がアフターコロナではさらに大切になるでしょう。いずれにしても、駅ビル全体をリ・デザインすべきときに来ているのではないでしょうか。
田村:オンライン・オフラインの大きな違いは「人」がいるか、いないかということですか?
臼井先生:見落としてはいけないことは、オンラインであってもカリスマ店員と会話はできます。すでに中国ではライブコマースが盛り上がっています。店員とのフィジカルな触れ合いもあるが、一方で、オンラインでのやりとりもできます。そこは使い分けになるかと思います。
田村:日本においても、コロナ禍でライブコマースを始めた企業も多いですね。そうなると、駅立地の価値は「人が集まりやすい」という点になりますかね?
臼井先生:郊外型のショッピングモールでは、そもそも人が集まりにくい場所に出店し、そこに集客をしています。これにはかなりのノウハウが詰まっています。凄いことだと思います。私がアジア諸国で調査しているイオンモールは、これから開発が本格化するような辺境の地にあえて出店しています。「これから幹線道路が通る予定です」みたいな立地ばかりです。逆にそういうところは、地元の政府からすると開発の目玉としてショッピングモールの出店に期待しています。ゼロを一にする努力ですね。これは並大抵のことではありません。イオンモールには立地優位はありませんので、まずは徹底した魅力づくりから着手します。わざわざ1時間かけてまで来店いただくのですから、その場所でなければ存在しないショッピング体験やエンターテイメントを創造することから始めるのです。
駅直上の商業施設は、本来の価値に原点回帰すれば良いと思います。駅直上の商業施設は、郊外型ショッピングモールとはビジネスモデルが全く異なります。その場所(立地)が内在する独自の経営資源をうまく活用してビジネスモデルを構築すべきですね。キーワードは「毎日」です。

「周遊・回遊といった館内行動によって健全な精神は保たれる」
田村:数年前より「ウォーカビリティ(Walkability)」という言葉が、まちづくりにおいて注目されてきましたが、やはり自分の足で欲しいものを探すといった身体的活動がないと人間の精神に影響を与えるものだと思われますか?
臼井先生:そう思います。外に出ないとね。みんな、走ったり歩いたりしているでしょう。身体的活動は人間にとって不可欠ですね。
田村:シニアの方がわざわざショッピングに出かけるのは、身体と精神の両方の充足をするためですよね。
臼井先生:その通りです。霊長類学者で京都大学総長の山極壽一先生が、人間の「共感力」について解説なさっています。ゴリラやオランウータンとは異なり、熱帯雨林を出て、環境への適応を迫られた人間は、群れからチームへの進化を必要とした。その進化の過程で人間はお互いに共感し、協力する道を選んだというのです。
今後も人間は、人と人との関わりなくして生きていけないと思います。共感し、協力しあってさまざまな課題に取り組む、共に楽しむのが人間ですよね。分断されたオンラインでは限界がありますね。
田村:「人間回帰」がテーマになりそうですね。身体的活動ということでは、周遊、回遊することの楽しさが商業施設にはあります。
臼井先生:ショッピングモールでは、開店時間に軽装で来店し、運動がてらに館内を三周して帰る方もおられますよね(笑)。
田村:駅ビルには、ほとんど使われていない階段があります。例えば、この段数で何カロリー消費しますといった階段を使った館内の回遊プロモーションとかありかもと思いつきました。
臼井先生:以前、田村さんがマーケティングの手法として「ネガティブなものをポジティブに変える」ことについて学生に解説なさっていましたよね。まさにその通りで、そうして新たな市場価値を見出していく、これがまさに成熟社会におけるマーケティングです。いいと思います。

「お客様が求めるものを再度見つめ直し、コンテンツをつくる」
田村:リアルな場において、身体的活動が満たされる仕掛けはぜひ企画してみたいと思いました。これは買い物だけでなく、レジャー・余暇活動においても相通ずるものですよね。
臼井先生:レジャー・余暇活動は、これまでも随分と多様化してきましたが、家でもゲームや映画鑑賞で余暇活動はできますよね。このようにレジャーにとっても、かなりの数の選択肢が存在する中で、いかに特定の活動を選んでいただくのかが課題です。そこでしかないコト、いまだけしかできないコトをいかにつくれるかということは、買い物と同様の課題ですね。
たとえば、イオンモールには、必ずしも好立地ではない場所で、一から集客してきたノウハウがあります。それはイベントですね。館内外には広場やスペースが多くあり、スペースごとに細かくイベントを配置して、それらがすべて連動し、さらに買い上げ率につながるプログラムがうまく組まれています。結局は、楽しい空間づくり、行ったら常に新しいものがある、それしかないと思います。コンビニだって、常に新商品をおいて目新しさを演出していますよね。これからは、リアルな場を使ったプロモーションやイベントにおけるクリエイティビティがますます重要になると考えています。
田村:コンテンツが重要ということですね。
臼井先生:そう、コンテンツです。元USJで、現在は刀というコンサルティング会社を率いる森岡毅さんのお話は有名ですね。もともとUSJは、E.T.やジュラシックパーク、ターミネーターといったハリウッド映画の強力なコンテンツをもつテーマパークだったのですが、彼は「それをUSJに来ているお客さんは本当に求めているのですか?それは押し付けではないか?」ということを問い直しました。そこで、主な来場者であった若者やインバウンドの観光客を楽しませるために、彼が仕掛けたのは、ジェットコースターを逆に走らせたり、ハロウィンナイトをやったり、進撃の巨人とコラボレーションしたりと、ハリウッドにこだわらず、そこに来るお客さんを喜ばせるコンテンツを一から考えて、どんどん提供することでした。駅も同じだと思います。コンセプトを一から考案し、コンテンツをいかに創り変えるか。それによって生活者をいかに楽しませるかが鍵ですね。
田村:お客さんが何を求めているか?を問い直すことが重要ということですね。
臼井先生:立地ごとに、駅ごとに、お客さんの求めているコンテンツやサービスは異なると思います。そこをつきつめていくが重要です。イオンモールは、近隣の病院と組んで無料診療をやったり、近くの小学校の作品を展示したりと地域密着の姿勢を徹底しています。館内イベントにはこのような地域密着のイベントも含まれます。このような取り組みにより、心理的距離が近づき、信頼関係が生まれることによって、地域のお客さんとモールとの間に強い関係性が構築できるのです。まさに共感力ですね。
これなくして、アフターコロナ、ウィズコロナにおいて、リアルな場への集客力を従来通り獲得するのはかなり難しくなるでしょう。そもそも外出せずともオンラインでいろんなことができることを生活者は知ってしまったわけです。これまで以上に生活者はリアルな場を選別するようになると思います。もちろん、その際には店舗における感染症対策も安全面において重要な要因になりますね。
商業施設における展示やイベントの高度化は日本の消費文化のひとつであるといっても過言ではありません。世界の商業施設にはあまり見られない現象だと私は考えています。誰でも楽しめる「館内イベント」が、日本が世界に誇る日が来るのも遠くはありませんね。

「地元回帰への機会。鉄道会社はそのコーディネイトによって沿線上の移動を創る」
田村:このコロナ禍による移動範囲の制約によって、地元に改めて目を向けていただき、関係性をつくる良い機会だと感じました。
臼井先生:地域を深堀していくことがトレンドになっていくと思いますし、すでにそうなっていると思います。それには、自分が住んでいる地域の再発見をナビゲートするサービスが求められますね。Googleで提供されている地図情報サービス等を使えば、行きたいお店をピンポイントで探し当てることができます。Googleを使えば、地元にいい店があってもそれを探さずに外へ行ってしまうこともあれば、逆に他からの来客の可能性も高まっているわけです。自分が住んでいる地域のことを、もっと深堀するのを支援することが大切です。地元には気づいていないお店っていっぱいありますよね。それを沿線でつなげてあげると沿線上での移動が起き、私たちが研究している沿線多拠点生活にも現実味を帯びてきますね。
田村:鉄道会社は、移動の制約がある今だからこそ、もう一度沿線の魅力を掘り起こしてそれを伝えていくべきだと感じました。
臼井先生:そのとおりです。多くの生活者は、今までは、情報過多で、しかも通勤や残業によって家で過ごす時間が限られていたので、地元は素通りして開拓してこなかったのだと思います。Googleに掲載されるとすべてがフラットで無機質な情報になってしまうので、地元感、地域感というものを正確に編集して、地域の生活者へ「共感」をもって伝えられるのは、その地域の鉄道会社の役割ではないでしょうか。
田村:まさにそうですよね。
臼井先生:何の変哲もない公園も、使い方によって新しい楽しみ方が創作できる、そんなこともあると思います。そういう遊びの演出とか、クリエイティビティということも大事でしょうね。我々が知らないだけで、隣駅のあの公園には他にはないような面白い遊具があるのかもしれません。それを伝えるのは、行政ではなかなか難しい。半公共といえる鉄道会社が担うべきだと思います。
田村:今こそ沿線の人々とのエンゲージメントを深める機会ですね。
臼井先生:未来の駅は、その地域のシンボルであり、みんなが目指す場所にならないといけませんし、そこに住んでいる生活者の皆さんはそれを期待していると思います。毎日駅に行って、毎日散策するというライフスタイルにおいて、生活者の期待に寄り添うようなサービスをどう展開できるかということにつきるのかと思います。乗降客数の減少や、オンラインで様々なことができるようになってくると、どうしても駅の場としての価値が相対的に低下してくることは避けられません。だからこそ、その中で選んでもらうにはどうしたらいいのかを今こそ真剣に考えなければならないのではないでしょうか。
私たちが提唱する「LDKステーション」(*)のように、ゆるやかなつながりの場をつくり、人と人とをつなぐコミュニティを地道に作っていくということが、駅に来てもらうためのひとつの仕掛けだと考えます。そこでは「価値共創」がキーワードになるでしょう。事業者が与えるのではなくて、そこに参加する生活者の皆さん同士が、化学反応を起こして、新しい価値を見出し、作り込んでいく、その場を演出すること、お手伝いすることこそが鉄道会社に求められているのではないでしょうか。
田村:私たちが提唱しているLDKステーションを起点とした沿線多拠点生活の可能性が高まった感がしますので、ぜひ実現させたいと思います。今回は、貴重なお話ありがとうございました。
(完)
*田村高志・吉村寿垣・立花徹也・増田光一郎・甲斐美由紀・臼井哲也(2020)「未来の駅が創造する価値の研究-LDKステーションと沿線多拠点生活の可能性-」『日経広告研究所報』310号、311号